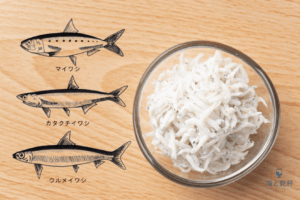ブリの切り身や刺身に、細長いミミズのような「糸状の虫」を見つけて驚いた経験はありませんか?
これは「ブリ糸状虫」または「ブリ線虫」と呼ばれる寄生虫で、毎年SNSやネットでも話題になる存在です。
「これってアニサキス?」「食べても大丈夫?」「クレームをするべき?」と不安になる方も多いはず。
実はこの糸状虫、見た目は気になりますが、間違えて食べてしまっても人体への害はほとんどないと言われています。
この記事では、ブリ糸状虫の正体や安全性、見分け方や調理のポイント、さらに食べてしまった場合の対処法まで、分かりやすく解説します。
ブリの糸状虫(ブリ線虫)とは?
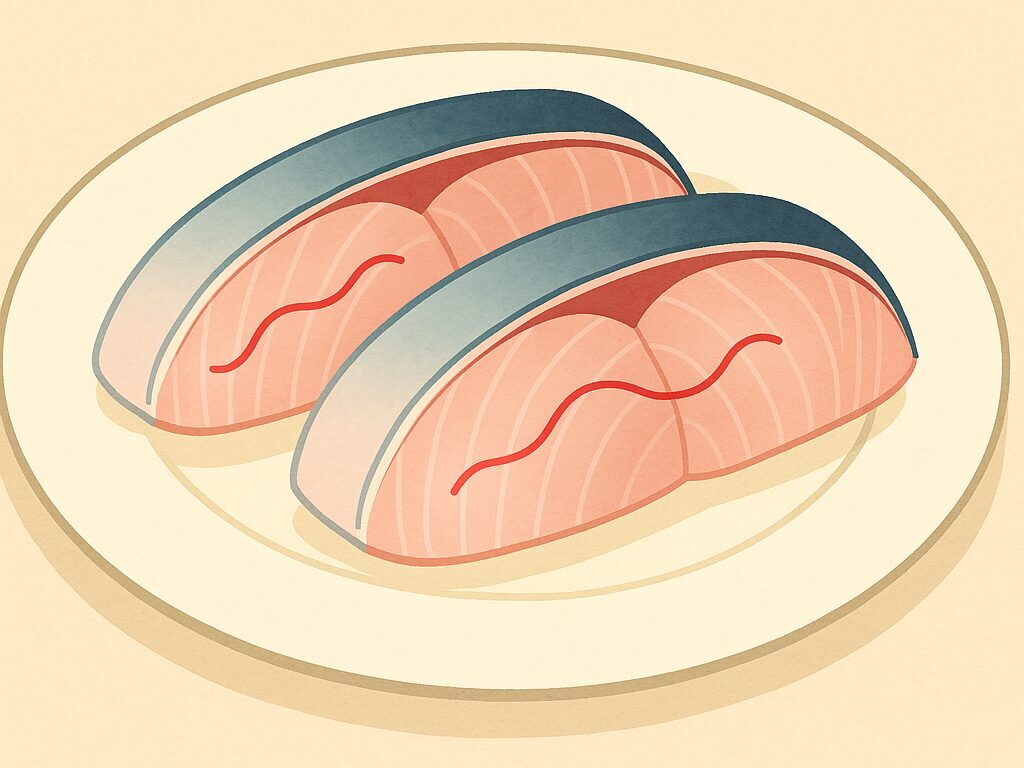
ブリの身から出てくる細長い橙赤色の虫、「ブリ糸状虫(しじょうちゅう)」は、ブリ線虫とも呼ばれ、ブリやハマチ、ワラサなどの青物によく見られる寄生虫です。
刺身や切り身で発見すると驚く方も多いですが、実は珍しいものではありません。
特に天然ブリではよく見つかりますが、食中毒などの健康被害はほとんど報告されていません。
ここでは、ブリ糸状虫の正体や特徴、安全性について解説します。
 堀江
堀江食べても大丈夫とはいえ、気持ち悪いニョロニョロした見た目にびっくりしますよね。
ブリ糸状虫はどんな寄生虫?特徴・大きさ・色
ブリ糸状虫(学名:Philometroides seriolae)は、体長数cm~20cmほどになる橙赤色の糸状の寄生虫です。中には50cm超えることもあります。
見た目はミミズのように細長く、筋肉や体腔にとぐろを巻いたように寄生します。
1匹だけでなく複数寄生していることも珍しくありません。
ブリ糸状虫の特徴
- 糸のように細く、長さは5cm〜長いもので50cm以上
- 色は魚の血を吸っているため橙赤色
- ほとんどがメス(オスは非常に小さい)
筋肉の中に見つかることが多く、切り身に混じることで発見されることが多いです。
ブリ糸状虫の生態と発生しやすい時期・季節
ブリ糸状虫は、主に春から夏の時期に多く見られる寄生虫です。
天然のブリが成長し、エサとなる小魚やプランクトンを多く食べる季節に体内に入り込み、筋肉や体腔に寄生します。
- 0歳魚(小さなブリ)にはほとんどいない
- 色は魚の血を吸っているため橙赤色
- 春〜夏にかけて水温が高くなる時期に目立つ



特に天然の大型ブリをさばくと、身の中に見つかるケースが多いです。
天然と養殖での発生状況の違い
天然ブリと養殖ブリでは、ブリ糸状虫の寄生率に大きな差があります。
- 天然ブリ
-
天然ブリは自然界で様々なエサを食べるため、寄生虫がつきやすい環境。
特に成長した大きな個体ほどブリ糸状虫が多くなります。
- 養殖ブリ
-
養殖ブリは管理されたエサや水質環境で育てられるため、寄生虫の寄生リスクが非常に低いです。
養殖ものからブリ糸状虫が見つかることはほとんどありません。
スーパーなどでブリ糸状虫を見かける場合は、ほとんどが天然ブリや天然に近い養殖方法で育てられた個体と考えられます。
品質に問題はありませんが、見た目の気持ち悪さからどうしても気になる場合は、養殖ブリを選ぶのも一つの方法です。
ブリ糸状虫は食べても大丈夫?人体への影響と安全性


ブリの切り身で赤い糸のような寄生虫(ブリ糸状虫・ブリ線虫)を見つけて、「これ、食べても大丈夫なの?」と不安になる方も多いはずです。
ここでは、ブリ糸状虫を誤って食べてしまった場合のリスクや、安全性について、厚生労働省・農林水産省など公的情報もあわせて詳しく解説します。
参考リンク
農林水産省 Q&A ブリを調理するとミミズのようなものが出てきたが、食べても大丈夫ですか。
ブリ糸状虫を食べたらどうなる?症状やリスク
まず結論から言うと、日本国内でブリ糸状虫を食べて健康被害や食中毒が起きた例はありません。
厚生労働省や農林水産省の調査でも、ブリ糸状虫は人体に寄生せず、万が一食べてしまっても体内で生き残ったり、症状を引き起こすことはほぼないと報告されています。
- 食べても体内で害を及ぼすことはほぼなく、消化されて排出される。
- これまで健康被害や食中毒の事例は、日本国内で報告されていない。
ブリ糸状虫はブリなど魚の筋肉にだけ寄生する寄生虫であり、人の体内で生きることはできません。仮に刺身や加熱した切り身と一緒に食べてしまっても、消化管で分解され、自然に排出されます。
ただし、見た目のインパクトが強いため、心理的な抵抗感や不快感はあるものの、健康面での心配はいりません。
アレルギーや食中毒の可能性は?
糸状虫は、アレルギー症状や食中毒を引き起こすリスクはほとんどありません。
アニサキス幼虫は激しい腹痛やアレルギーを引き起こすことで有名ですが、ブリ糸状虫にはそのような毒性や危険性は認められていません。
ただし、ごくまれに体質によってアレルギー反応を起こす可能性もゼロとは言い切れません。しかし一般的には問題ないと考えられています。



気になる方やアレルギー体質の方は、糸状虫が入った部分をしっかり取り除き、加熱調理することでより安心して食べられます。
子供・妊婦・高齢者でも大丈夫?
子供・妊婦・高齢者が糸状虫を誤って食べてしまっても、健康被害の心配はほぼありません。
糸状虫は人間の消化管で消化され、体内で生き残ることはありません。
また、注意したいのは糸状虫ではなく、アニサキスなどの他の寄生虫です。
アニサキスは腹痛やアレルギー症状を引き起こす場合があるため、生食する場合は冷凍や加熱などの対策をしっかり行いましょう。



食べても大丈夫ですが、見た目が気持ち悪いのでストレスは感じてしまうかもです。


ブリ糸状虫とアニサキスの違い・見分け方


ブリや青魚に見られる糸状虫と、食中毒の原因として有名なアニサキスは、まったく別の寄生虫です。
見た目が似ているため不安になりやすいですが、特徴を知っておくと安心して見分けることができます。
アニサキスとの比較!見た目・色・大きさ・動き
| 寄生虫の種類 | 色・見た目 | 大きさ | 動き | 主な寄生部位 | 人体への影響 |
|---|---|---|---|---|---|
| アニサキス | 白色~半透明・ツヤあり | 長さ2~3cm、太さ0.5~1mm | 生きていればよく動く (クネクネ) | 内臓、筋肉の表面や内部 | 害あり (激しい腹痛、アレルギーなど) |
| ブリ糸状虫 (ブリ線虫) | 薄いピンク~赤色~茶色、やや透明 | 長さ5~50cm 太さ2~3mm | ほとんど動かない (死んでいることが多い) | 筋肉の中 (切り身の内部) | 無害 |
アニサキスは白く短い・動く、糸状虫は赤~茶色で長い・ほとんど動かない、という違いが特徴です。


ブリ糸状虫の見つけ方・見分け方
刺身や切り身の中に、細長く赤茶色の糸のような虫が見つかった場合、それは糸状虫(ブリ糸状虫)である可能性が高いです。
糸状虫は包丁で魚をカットした際、断面に赤い線のように現れることも多く、筋肉の中に長く入り込んでいるのが特徴です。
見分けるポイントは「長さ」「色」「動き」の3つ。
糸状虫は長く(5〜30cmが多い)赤っぽい色をしており、魚から取り出した時点では動かない(死んでいる)ことがほとんどです。
一方で、短く白っぽくてクネクネ動くものはアニサキスで、人体に有害な場合があるので注意が必要です。
もし見た目で判断がつかない場合は、購入した販売店や詳しい人に相談するのも安心な方法です。
ブリ糸状虫を見つけたとき・食べた場合の対処法


ブリの糸状虫(ブリ線虫)は人体に害がないとされていますが、見つけたときはやはり気になるものです。
ここでは、ブリ糸状虫を見つけた時や、万が一食べてしまった場合の対処法、安全に食べるための加熱・冷凍のコツ、調理時の注意点について解説します。
ブリの糸状虫を見つけた時の対処法
ブリ糸状虫を発見したら、「どうしたらいいの?」と不安になる方も多いですよね。安心して食べるための対処法をまとめました。
目視で確認&取り除く
ブリ糸状虫は赤〜ピンク色で、太めの糸のような見た目です。切り身や刺身の断面を明るい場所でよく観察し、見つけた場合はピンセットなどで丁寧に取り除きましょう。
釣った場合は内臓処理を早めに
釣りたてのブリは、できるだけ早く内臓を取り除きましょう。内臓を残したままだと、寄生虫が筋肉に移動してしまう場合があるため、現場で素早く処理するのがコツです。
加熱・冷凍でしっかり予防
加熱調理すれば寄生虫は死滅します。しっかり火を通して食べると安心です。また、家庭用の冷凍庫(-20℃)で24時間以上凍らせることでも死滅します。刺身で食べたい場合も、冷凍処理を行えばより安全です。
購入時のチェック
スーパーや魚屋で購入した場合も、念のため断面やパックの中をチェック。もしもブリ糸状虫を見つけた場合は、その商品を持ってお店に相談したり、返品や交換をお願いしてみるのも一つです。



購入前だと交換してくれるかもしれません。
加熱・冷凍で駆除できる?
ブリ糸状虫は加熱や冷凍によって死滅するため、しっかり火を通せば問題ありません。
一般的に、中心部までしっかり加熱(70℃以上で数分)することで確実に駆除できます。冷凍の場合も、-20℃以下で24時間以上凍結すれば安全性が高まります。
刺身など生食の場合は、ブリ糸状虫がいないかよくチェックしましょう。
糸状虫は筋肉内に長く寄生していることが多いため、切り身の断面や赤い線状の部分を丁寧に観察するのがポイントです。



アニサキスなど他の寄生虫対策にもなりますね!
調理時の注意点(刺身・照り焼き・揚げ物・焼き魚など)
刺身、焼き魚や照り焼き、揚げ物や煮魚など、どの調理法でも気になれば調理前に糸状虫をピンセットなどで取り除きましょう。
特にお子さんや高齢者、妊婦の方は、心配になりますよね。念のため加熱調理を選ぶと安心です。
ブリ糸状虫はどんな魚に多い?ブリ以外での発生例
ブリ糸状虫はブリによく見られる寄生虫ですが、実は他の魚でも発生例が報告されています。
どんな魚で見つかりやすいのか、また季節や地域による違いについても解説します。
ハマチ・ワラサ・カンパチ・ヒラマサ・カツオなど
糸状虫は、ブリやハマチ、ワラサ、カンパチ、ヒラマサなど、ブリ属の魚で見つかります。
これらはいずれもスズキ目アジ科の仲間で、身の中に赤っぽい糸状のものが入っている場合は糸状虫の可能性が高いです。
カツオの筋肉にもカツオ糸状虫と呼ばれる寄生虫が発見されることがあり、こちらも人体には基本的に害はありません。
また、天然魚の方が発生しやすく、養殖魚では比較的少ないとされています。



切り身の内部に赤い糸状のものが見えたとき、「えっ!?」と驚く方も多いですが、こうした魚種では糸状虫が入っていることが珍しくありません。
とくに天然ものや、春から秋にかけての暖かい時期によく見られます。
まとめ:糸状虫がいてもブリは食べられる!正しい知識で安心を


ブリ糸状虫(ブリ線虫)は、人体には害がなく、取り除けば安全に食べられる寄生虫です。
魚をさばいて赤い糸状のものを見つけると驚いてしまいますが、厚生労働省や東京都保健医療局も「食べても健康被害はない」と案内しています。
ただし、似ている寄生虫「アニサキス」には要注意です。
アニサキスは白くて短く、動きが活発な特徴があり、食べると激しい腹痛などの食中毒を起こすことがあります。見た目や動きが違うので、よく観察して区別しましょう。
漁の現場でも、糸状虫が入っている魚はよく見かけますが、包丁で取り除いたり、しっかり加熱・冷凍すれば安心、ということを意識していれば大丈夫です!



安心して魚の世界をもっと楽しんでもらえたらうれしいです。


.png)
.png)